キャメルのしょ〜かい〜っス
キャメルは耽美派プログレの最高峰です。日本での人気は高く、キング・クリムゾン、ピンク・フロイド、YES等に引けを取らない人気があると思います。ハーバー・オブ・ティアーズ発表後に日本公演も行っています。
ほんとに、プログレってのは自分で聴いていても一つのジャンルにまとめるのはおかしいと思いますな〜。キングクリムゾン、P.F.M、キャメルといったバンドを一まとめにするのは無理があります。曲が長いというのは確かに共通項かもしれないけど、クリムゾンとキャメルを同じフィールドに組み込むにはね〜
だから、プログレというのはある一つのバンドを聴いて肌に合わないというには早すぎるんですよ。
わしの例で言うと、ピンク・フロイドは少しきついです。「狂気」を聴いたんですけど…サイケすぎます。まあ、元が葉っぱ吸いながら聴くための音楽だからね〜(-_-;)
そんなんで、キャメルにはキャメルなりの肌が合う人合わない人がいるはずなのです。
キャメルはイギリスのバンドで、冒頭にも書きましたが、叙情派、耽美派という区切りで語られるバンドです。ファンタジー・ロックと呼ぶ人もいますな。ただ、甘いというわけではないので注意が必要です。
どちらかというと、純朴、素朴といった形容詞、郷愁を誘うというのもありです。鬱蒼と茂った森や霧のかかった高原といったイメージですな〜。
「今日あいつに惚れてしまった」とか「なんか最近うまくいかないな〜」とか「社会は悪に満ちている!」といった人間の感情や社会を描写するのではなく、雄大な自然の風景を描写しているという感じです。
わしはそんなキャメルの音楽にいつも癒されています。疲れた人にキャメルは効くはずです(笑)
| CAMEL/キャメル
1973年発表の1st |
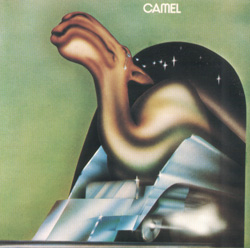 なんか、ださいジャケットですな・・・(苦笑)まあ、そんなことは気にしないで紹介いきますか・・・ なんか、ださいジャケットですな・・・(苦笑)まあ、そんなことは気にしないで紹介いきますか・・・このアルバムが日本のプログレファンから絶大な人気と支持を集めているキャメルの記念すべきデビューアルバムです。 ちなみに、デビュー自体は72年のシングル「Never Let Go」でしています。 ものの本によると当初キャメルはサンタナのようなサウンドを目指していたらしいが、そんなにラテンサウンドは入っていないように聴こえるのだが・・・(謎) 正直な話、まだ、この作品ではキャメルとしてのアイデンティティは確立されていないように思えました。英国のバンド特有の湿り気や翳り、アンディ・ラティマーの流麗なギタープレイ、郷愁と哀愁に満ちたメロディー、ファンタジーロックとも形容される幻想的な雰囲気といった後のキャメルが持つことになる要素は随所に感じ取ることはできますが、まだ迷いが感じられます。アルバム全体としてはまだキャメルカラーに染まりきっていないということです。 でも、名盤と位置付けさせていただきます。あるバンドが絶頂期にあった時の作品が名盤と呼ばれるのは当然だが、その後のキャリアに影響を与えたことなども考慮に入るのならこのデビュー作も紛れもなく名盤といえると思う。キャメルの出発点としても、内容的にも作品全体の統一感などを無視すれば素晴らしいです。 で、聴き所は5曲目のデビューシングル曲でもある「Never Let Go」でしょう。その後のキャメルのライブでは必ずといっていいほど演奏されるようになった曲です。ラティマーがギターソロ以外をアコギで通しているのが興味深い。しかもイントロや中間部以外はアルペジオでもなく普通にコードをかき鳴らしています。後のラティマーからするとえらくシンプルな感じです。ギターに期待すると少し拍子抜けするかも?やっぱり、この曲ではピーター・バーデンスのキーボードがキャメルっぽさを演出しているみたいです。初期キャメルでのピーター・バーデンスの重要性をあらためて確認した次第です。ちなみに、ライブ盤でこの曲を聴いたところラティマーのギターはもっと自己主張をしていました。アコギでもなかったし。 1曲目はけっこう後のキャメルにつながるような感じの曲です。中間部でラティマーがギターを唸らせながらギターソロに突入するスタイルはここからなんですな。後半のコーラスもスノーグースっぽいし。 4曲目はかっこよいのだけど微妙にキャメルっぽくない感じを醸し出していて違った意味で面白い曲です。 ちなみにヴォーカルは専任でなく、ラティマー、バーデンス、ダグ・ファーガスン(ベース)の三人が交代で歌ってます。三人とも歌は取り立てて上手くないです。というか、下手かも?まあ、インスト主体のバンドだから全く気にならないです。 |
| Mirage/ミラージュ(蜃気楼) 1974年発表の2nd |
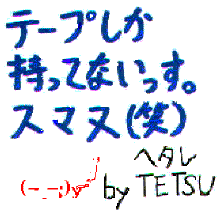 実はスノーグースよりお気に入りかもしれない! 実はスノーグースよりお気に入りかもしれない!何度も書いてますが、コンセプトアルバムは苦手なんです。それに、このアルバムには「レディ・ファンタジー」が収録されてるからね(^。^) |
| The Snow Goose/スノー・グース(白雁) 1975年発表の3rd |
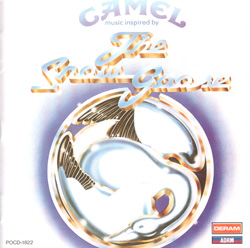 この同名の小説を基に作られたコンセプトアルバムはプログレファンの間ではキャメルの最高傑作と呼ばれています。故に本も買って聴きましょう(爆) この同名の小説を基に作られたコンセプトアルバムはプログレファンの間ではキャメルの最高傑作と呼ばれています。故に本も買って聴きましょう(爆)え?お前は買ったかって? ……もちろん小説も買いましたよ。 では、作品のコンセプトの方をもう少し詳しく書いてみますか。 基となった小説はアメリカ人作家ポール・ギャリコの作品「スノー・グース」で1941年発表です。舞台は第二時大戦中のイギリスです。灯台に住み、野鳥を愛する心優しい身障者の画家フィリップ・ラヤダーと少女フリスとの関係を描いています。ストーリーをこと細かく書くのも無粋なんでこの辺にとどめておきますが、このアルバム聴きながら読むと泣けます。小説自体は短編なのでうまく読むとアルバムのランニングタイムとあまり変わらない時間で読み終えることが出きるでしょう。 文庫本が新潮社から出ている(いた)筈なのでキャメルの「スノーグース」を持っている人、買いたいと思った人は小説もチェックしてみてはどうでしょうかな?
で、アルバムのサウンドの方はというと、本当にファンタジーロックの頂点と呼ぶことが出来ます。淡く優しい音が全身を包み込んでくれます。終盤の劇的な展開には言葉を失いますし、うまく小説とリンクしていて音でストーリーを描ききっています。 |
| Moon Madness/ムーン・マッドネス「月夜の幻想曲」 1976年発表の4th |
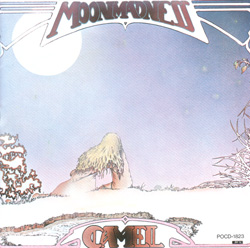 若干キーボードの活躍度が高いと思う。 若干キーボードの活躍度が高いと思う。キーボードはムーグシンセサイザーなどの古いものなので、かなり独特な音色です。敢えて文字で表現するなら「ぐにょ〜」って感じの音です(笑) 多分嫌いな人もいると思います。 それでも、流麗なギターサウンドも健在なので悪くはないです。 ラストの「Runar Sea/月の湖」は中間にキーボードの退屈なパートがあるものの、後半のギターパートには圧倒されます。 |
| Rain Dances/雨のシルエット
1977発表の5rh |
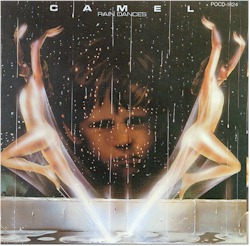 キャラヴァン、ハットフィールド&ノースに在籍していたRichard
Sinclair(b、Vo)が加入し、牧歌的で幻想的なそれまでの作風に、ジャズ、フュージョン系の都会的で洗練された雰囲気が加わるようになった作品。次作のブレスレスの方が同じ傾向の作品としては演奏もスリリングで完成度は高いと思うが、プログレっぽさがあまりないという点では初心者には聴き易いかも知れない。5曲目の「UNEVENSONG」は結構かっこいいです。後半の泣きメロもいいし。 キャラヴァン、ハットフィールド&ノースに在籍していたRichard
Sinclair(b、Vo)が加入し、牧歌的で幻想的なそれまでの作風に、ジャズ、フュージョン系の都会的で洗練された雰囲気が加わるようになった作品。次作のブレスレスの方が同じ傾向の作品としては演奏もスリリングで完成度は高いと思うが、プログレっぽさがあまりないという点では初心者には聴き易いかも知れない。5曲目の「UNEVENSONG」は結構かっこいいです。後半の泣きメロもいいし。ちなみに、ジャケット…理解不能(笑) |
| Breathless/ブレスレス−百億の夜と千億の夢− 1978年発表の6th |
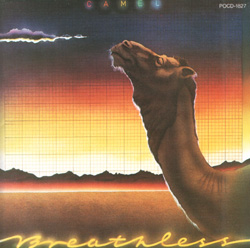 この作品はお勧めです。大作はあまりなく肩肘張らずに聴ける癒し系キャメルっす。とても聴いていてリラックスできるアルバムだと思います。 この作品はお勧めです。大作はあまりなく肩肘張らずに聴ける癒し系キャメルっす。とても聴いていてリラックスできるアルバムだと思います。HR/HMも好んで聴いているTETSUですが、いつも、テンポの速い曲やひどくディストーションのかかったギターを聴いているわけではありません(^_^;)やっぱり、聴く曲にもある程度は緩急をつけないと、疲れちゃいます。 もちろん、気持ちを昂ぶらせたいときには速い曲を聴くんですが、いつも気持ちを昂ぶらせている人間なんてチョットいやですよね〜 この作品を癒し系とか、リラックスして聴けるとは書きましたが、単にポップでソフトな作品というわけではないです。難解で複雑なイメージのプログレっていう感じではないけど、少し、曲の展開などが風変わりで面白い。オルガン風の音色のシンセとかフルートの素朴な調べが気品のある優しさを演出しています。 曲ごとに注目すると、70年代後半というプログレムーブメントも完全に下火になった時期であるという背景もあるのかもしれないけど、1.5.9曲目といった小曲がキラリと光ってますね♪ 大曲に関しては2曲目のエコーズ(残響)が評判いいらしいです。ファストテンポでなおかつ展開が一度変わって戻るというイントロはとても印象的です。まあ、イントロが1分40秒あるから展開が変わるのだけど(笑)ただ、いい曲なんだけど、イントロはよしとして中間の展開がちょっとたるいかも? やっぱり、このアルバムは、4分程度の長さだけどキャメルとしての主張をしている小曲に注目すべきですね。 エコーズや6曲目の哀メロのきいた大曲、8曲目のフュージョンぽい大曲も決して悪くはないんだけどね(^_^;)
|
| Harbour Of Tears/ハーバー・オブ・ティアーズ-港町コーヴの物語-
1996年発表 |
 聴いてると切なくなるアルバムです。聴き終わると感動するアルバムです。 聴いてると切なくなるアルバムです。聴き終わると感動するアルバムです。19世紀のアイルランドを取り巻いていた悲劇的な状況を歌ったコンセプトアルバムです。12曲目が個人的には好きですね。 ちなみに、初めて買ったキャメルのアルバムがこれになります(発売は96/2で買ったのは96末)。そして、このアルバムには感動しました。でも、70年代の作品と聴き較べると・・・これってバンドの作品じゃあないよね・・・アンディ・ラティマーのギターとボーカルを軸にセッションミュージシャンやらを雇い、クラッシックのプレーヤーまでも雇って作ったソロ、又はプロジェクトだよね?・・・そこにあるのはラティマーの絶対的な意思だけであり、ほかのミュージシャンはそれに従うという構図が成り立っていて、バンドじゃあないです。それが今現在の正直な感想です。まあ、実際、オリジナルメンバーもラティマーしかいないのだしね。もちろん、作品としての質は保証するけど。 |
| Rajaz/ラージャーズ〜別れの詩〜 1999年発表 |
この作品、キャメルの作品としてみると…異色だろうとライナーで和田誠氏は書いています。それについてはわしもそうだと感じました。 |